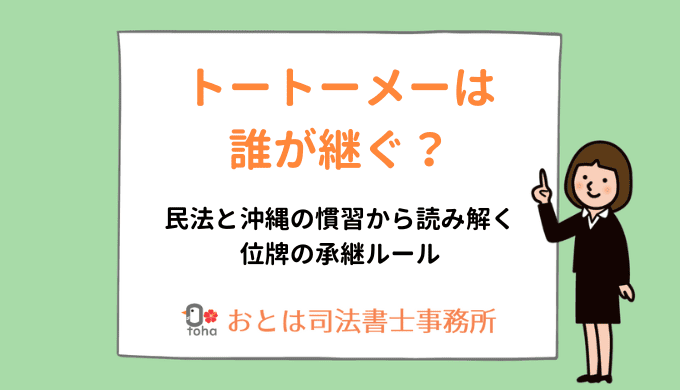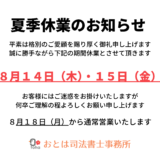沖縄の相続で必ず話題になる「トートーメー(位牌)の承継」。
この記事では、民法と沖縄の地域慣習の両方をふまえたトートーメー承継の基本を解説します。
目次
はじめに:トートーメーの承継、誰が継ぐのが正解?
沖縄で相続を考えるとき、「トートーメー(位牌)を誰が継ぐのか」は大きな関心事です。
けれど、いざ相続の場面になると「法的にどうなっているのか?」「揉めた場合はどうなる?」と疑問に思う方も少なくありません。
この記事では、民法上の位牌(トートーメー)の位置づけと、沖縄に根付く慣習の両方から、承継の考え方についてわかりやすく解説します。
トートーメーは法律上、どう扱われる?
結論から言うと、民法には「位牌は誰が継ぐべきか」という明確な規定はありません。
しかし、位牌は法律的には「物(動産)」とみなされ、相続財産として遺産分割の対象となる可能性もあります。
ただし、これに加えて重要なのが「祭祀財産」としての扱いです。
民法897条と「祭祀財産」という考え方
民法第897条では、次のように定められています。
民法第897条(祭祀主宰者の指定等)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
この「祭具」の中に位牌が含まれるとされ、民法上は「祭祀財産」として、慣習により承継者が決まるとされています。
つまり、「誰が継ぐか」は、被相続人の意思や、地域や家族の慣習が重視されるのです。
沖縄におけるトートーメー承継の慣習
沖縄では、原則として長男がトートーメーを継承するという考えが根付いています。
実際には以下のようなケースがよく見られます。
- 実家に住むことになった長男が仏壇やトートーメーを継承
- 仏壇のある実家に位牌が残る
- 実家を出る場合、仏壇ごと移すケースも
地域によって異なる「トートーメー」の継承ルール
「長男が継ぐ」という一般的な考え方はありますが、沖縄県内でも地域によって独自のルールが存在します。
たとえば、「長男に子どもがいない場合は次男の次男が継ぐ」というようなローカルルールがある地域もあります。
法的な根拠があるわけではないため、親族間でのトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
よくあるご質問(Q&A)
-
Q. トートーメー(位牌)は長男が必ず継がなければいけませんか?
-
→ 法律上の決まりはありません。ただし、沖縄では「長男が継ぐ」という慣習が広く根付いており、家族内での話し合いが重要です。
-
Q. 祭祀財産としての位牌は、相続税の対象になりますか?
-
→ 原則として、祭祀財産(位牌や仏壇など)は相続税の課税対象には含まれません。ただし、高額な仏具などについては例外となるケースもあるため、税理士などへの確認をおすすめします。
- Q. トートーメーの承継について、事前に指定しておくことはできますか?
- → はい、可能です。遺言書で祭祀主宰者(位牌を継ぐ人)を明示しておくと、相続人間のトラブル予防につながります。
 遺言書って必要? 名護・今帰仁で遺言作成をお考えの方へ【司法書士が解説】
遺言書って必要? 名護・今帰仁で遺言作成をお考えの方へ【司法書士が解説】
トートーメーをめぐる相続、どう備える?
承継トラブルを防ぐには、事前に家族で話し合っておくことが大切です。
また、以下の方法も有効です
- 遺言書で祭祀主宰者を明記しておく
- 仏壇やトートーメーについて書面で合意しておく
まとめ|トートーメーの承継は「法律と慣習」の両方で考える
-
- トートーメー(位牌)は民法上「祭祀財産」に該当する
- 沖縄では「長男が継ぐ」という慣習が根強い
- 地域によって独自のルールがある
- 将来のトラブルを防ぐには、遺言や書面による備えが大切